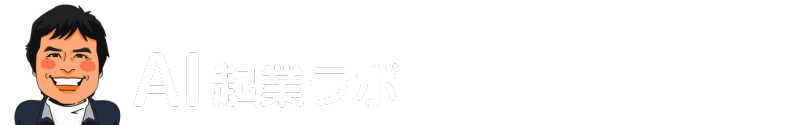TypeScript、React.js、Next.jsの基礎を3時間でマスターしましょう。プログラミングの基礎から最新のフロントエンド技術まで初心者に分かりやすく解説します。実用的なコード付きなので、初心者でもTypeScript、React.js、Next.jsで開発を始められます。
TypeScriptの基礎
TypeScriptの基礎を理解し、効率的な開発のためのスキルを身につけましょう。初心者にも分かりやすく解説します。
TypeScriptの基礎知識
TypeScriptは、JavaScriptを拡張した言語です。型の安全性と開発の効率化をもたらし、大規模アプリケーション開発に適しています。TypeScriptの基本概念を解説します。
TypeScript登場の背景
TypeScriptが登場した背景は、JavaScriptというプログラミング言語のいくつかの課題を解決するためです。JavaScriptはとても人気がある言語ですが、「動的型付け」という特性があります。動的型付けは、プログラムが実行される時まで変数の「型」(例えば、数値、文字列などのデータの種類)が決まらないことを意味します。動的型付けにより、プログラムに予期しないエラーが発生しやすくなります。
TypeScriptは、動的型付けの問題を解決するために「静的型付け」を採用しています。静的型付けでは、プログラムが実行される前に変数の型が決定され、エラーが事前に検出されやすくなります。静的型付けにより、プログラムの安全性が向上し、開発効率も大幅に改善されるのです。
また、TypeScriptは初心者にも扱いやすいように設計されているため、プログラミング経験が少ない人でも学びやすくなっています。TypeScriptはJavaScriptの利点を生かしつつ、より信頼性の高いプログラミングを可能にします。
TypeScriptとVisual Studio Code
TypeScriptの開発には、Visual Studio Codeが最適です。Visual Studio Codeは、Microsoftが提供する無料のコードエディタで、TypeScriptの開発に特化した機能を多く備えています。インテリセンス(コード補完)、リファクタリング、デバッグ支援など、TypeScriptを効率的に扱うためのツールが揃っています。初心者でも直感的に使えるインターフェースで、TypeScriptの学習やプロジェクトの開発が容易になります。
TypeScriptとJavaScriptの違い
TypeScriptとJavaScriptの違いを理解するには、「型システム」という概念を知る必要があります。型システムとは、プログラミング言語が変数(データを格納するための箱のようなもの)にどのように「型」(例えば数値、文字列などのデータの種類)を割り当てるかを定義するルールのことです。
JavaScriptは「動的型付け言語」です。変数の型が、プログラムが実行される時に決定されるという意味です。プログラムを書く時には型を明示的に指定する必要がなく、柔軟にコーディングができますが、意図しないエラーが発生しやすくなります。
TypeScriptは「静的型付け言語」です。プログラムが実行される前、つまり開発時に変数の型を指定する必要があります。静的型付け言語により、型に関するエラーを早期に検出でき、より安全にプログラムを書くことができます。特に、大規模なアプリケーションの開発や複数人でのチーム開発において、安全性が大きな利点です。
また、TypeScriptはJavaScriptの「スーパーセット」と呼ばれます。すべてのJavaScriptのコードが、TypeScriptと互換性があるということです。JavaScriptで書かれたコードは、TypeScriptでもそのまま動作するのです。JavaScriptの経験がある開発者は、TypeScriptを比較的簡単に学ぶことができます。
TypeScriptコマンドラインツールによるコンパイル
TypeScriptで書かれたコードを実際にウェブブラウザやNode.js(サーバーサイドのJavaScript環境)で実行するためには、コードをJavaScriptに「コンパイル」(変換)する必要があります。コンパイルを行うためには、TypeScriptのコマンドラインツールを使用します。
コンパイルのステップは以下の通りです。
- Node.jsのインストール: 最初に、Node.jsというプログラムをコンピュータにインストールします。Node.jsは、JavaScriptをコンピュータ上で実行するための環境を提供します。
- TypeScriptのインストール: 次に、NPM(Node.jsのパッケージマネージャー)でTypeScriptをインストールします。TypeScriptのコードを扱うためのツールがコンピュータに追加されます。
- コマンドラインからのコンパイル: インストールが完了したら、コマンドライン(コンピュータのテキストベースの操作インターフェース)を使ってTypeScriptのファイルをJavaScriptにコンパイルします。たとえば、
tsc helloworld.tsというコマンドを実行すると、helloworld.tsというTypeScriptファイルがhelloworld.jsというJavaScriptファイルにコンパイルされます。
コンパイルにより、ブラウザやNode.jsで実行可能なJavaScriptコードが生成されます。TypeScriptで書かれたプログラムが実際に動作します。
TypeScriptの型の定義
TypeScriptでの「型の定義」とは、変数や関数に特定のデータの種類(型)を指定することです。「型」とは、数字や文字列など、データの種類のことです。型の定義により、コードの安全性を高め、読みやすくできます。型の定義をすることで、コード内での予期しないエラーやバグを早期に発見し、特に大規模なアプリケーション開発やチームでの開発を容易にします。
変数
変数は「容器」のようなものであり、そこに様々なデータを入れることができます。TypeScriptで変数に型を定義する場合、変数名の後に「コロン(:)」と「型名」を書きます。その変数がどの種類のデータを扱うかを明確にします。型を定義することで、その変数に予期しない種類のデータが代入されるのを防ぎ、コードの信頼性が高まります。また、開発初心者でもコードの意図を理解しやすくなります。
以下は、TypeScriptで変数を型定義する基本的な例です。
let age: number = 25; // 「age」は数値型である
let name: string = "Alice"; // 「name」は文字列型である
let isActive: boolean = true; // 「isActive」はブーリアン型(真偽値、trueかfalse)である上記の例では、ageには数値、nameには文字列、isActiveには真偽値(trueまたはfalse)がそれぞれ代入されることが期待されます。型を定義することで、コードをより安全かつ明確にできるのです。
プリミティブ型
「プリミティブ型」は、前述の変数(容器)に格納できるデータの種類の一つです。TypeScriptのプリミティブ型には、数値(number)、文字列(string)、ブーリアン(真偽値、boolean)、null(値がないことを意味する)、undefined(定義されていない)、シンボル(symbol、ユニークな値を生成するための型)、ビッグインテジャ(bigint、非常に大きな整数を扱う型)などがあります。プリミティブ型は、変数に特定の種類の値を割り当てるために使用されます。
たとえば、数値を扱う変数にはnumber型を、テキストを扱う変数にはstring型を指定します。TypeScriptでは、プリミティブ型を使って変数を定義することで、適切なデータ型の使用を保証し、型の不一致によるエラーを防ぎます。特にプログラミング初心者にとって、TypeScriptの基本を理解する上で重要な要素です。
以下に、プリミティブ型を使った変数の例をいくつか紹介します。
let distance: number = 100; // 'distance'は数値を扱う
let username: string = "user123"; // 'username'は文字列を扱う
let isCompleted: boolean = false; // 'isCompleted'はブーリアン(真偽値)を扱う
let id: symbol = Symbol("id"); // 'id'はシンボル(ユニークな値)を扱う
let bigNumber: bigint = 9007199254740991n; // 'bigNumber'は非常に大きな数値を扱う上記の例では、各変数に適切なデータ型が指定されており、プログラムの安全性と明確性が向上しています。
配列
TypeScriptでは、「配列」を特定の型の要素が並んだリストとして定義します。
「配列」という概念は、プログラミングにおいてとても重要です。「配列」とは、同じ種類のアイテム(または「要素」と呼ばれる)が順番に並んだリストのようなものです。例えば、あなたの友達の名前を一覧にしたり、買い物リストを作るとき、それらは一種の「配列」と考えることができます。
配列は、同じ種類のデータを整理して保持するための便利なツールです。プログラマーはデータを簡単に管理し、エラーを防ぐことができます。
TypeScriptで配列を定義する方法は主に2つあります。どちらの方法も、配列内のすべての要素が同じ型であることを保証します。配列の定義により、数字のリストに文字列が混ざるようなことを防ぎ、プログラムのエラーを減らすことができます。
- 要素の型に続けて
[]を使用する方法: 配列を定義する最も一般的な方法で、読みやすいのが特徴です。例えば、数値の配列はnumber[]として定義し、文字列の配列はstring[]として定義します。
let numbers: number[] = [1, 2, 3, 4, 5]; // 数値の配列
let names: string[] = ["Alice", "Bob", "Charlie"]; // 文字列の配列- ジェネリック配列型
Array<要素の型>を使用する方法: より明示的で、特に複雑な型やネストされた配列(配列の中に配列がある場合)を扱う際に有用です。
let numbers: Array<number> = [1, 2, 3, 4, 5]; // 数値の配列
let names: Array<string> = ["Alice", "Bob", "Charlie"]; // 文字列の配列配列を使うことで、配列内の要素が一貫した型を持つことが保証され、プログラムの信頼性と管理のしやすさが向上します。
オブジェクト型
オブジェクト型とは、いくつかの異なるデータを一つにまとめて整理する方法です。オブジェクトを理解するためには、まず「キー(名前)と値のペア」という概念を知る必要があります。ある情報に名前をつけて、その名前(キー)に特定の内容(値)を関連付けることです。
例えば、あなたの友達に関する情報を整理するとき、彼らの名前(キー)と年齢(値)をペアにして記録できます。友達の名前がキーとなり、年齢がそのキーに関連付けられた値です。
TypeScriptでは、オブジェクト型を使って、キーと値のペアの集まりを作成します。オブジェクト型により、異なる種類のデータを一つのオブジェクト内に整理して保持することができ、データへのアクセスや管理が簡単になります。
簡単な例として、ユーザーの情報を保持するオブジェクトを考えてみましょう。このオブジェクトには「名前」と「年齢」という2つのプロパティ(特性)があります。
let user: { name: string; age: number; } = { name: "Taro", age: 25 };上記の例では、userオブジェクトにはname(文字列型)とage(数値型)の2つのプロパティがあります。オブジェクト内の各値が、特定の型を持つことが保証されます。
オプショナルなプロパティを持つオブジェクト型
オブジェクト型とは、いくつかの異なるデータ(プロパティと呼ばれます)を一つの単位でまとめる方法です。例えば、従業員の名前、年齢、職種などの情報を一つのオブジェクトで表現できます。
「オプショナルなプロパティ」とは、そのオブジェクトに必ず含まれる必要がない、つまり「任意の」プロパティのことを指します。普通、オブジェクトにはその全てのプロパティを定義する必要がありますが、オプショナルなプロパティは、あってもなくても大丈夫なプロパティです。
TypeScriptでは、オプショナルなプロパティはプロパティ名の後に?を付けることで定義されます。?は、そのプロパティがオブジェクトに含まれるかもしれないし、含まれないかもしれないということを意味します。
例えば、従業員の情報を保持するオブジェクトがあるとします。従業員の名前は必須のプロパティですが、年齢はオプショナルなプロパティとすることができます。この場合、従業員のオブジェクトに年齢が含まれていなくても問題ないということです。
オプショナルなプロパティにより、プログラマーはより柔軟にデータを扱うことができます。
let employee: { name: string; age?: number; } = { name: "Alice" };上記の例では、employeeオブジェクトにはageプロパティが含まれなくても問題ありません。
複雑なオブジェクト型
より複雑なオブジェクトを定義することもできます。
以下は、製品情報を保持するオブジェクトで、複数のプロパティ(id、name、price)を持つ、オプショナルなtagsプロパティ(文字列の配列)の例です。
let product: {
id: number;
name: string;
price: number;
tags?: string[];
} = { id: 1, name: "Pen", price: 1.5 };オブジェクト型を使用することで、データの構造を明確に定義し、コードの可読性と整合性が高まります。
any
TypeScriptのany型は、どんな種類のデータでも受け入れることができる特別な型です。any型を使うと、型のチェックを行わずに、任意の種類のデータを変数に割り当てることができます。anyにより、JavaScriptのような柔軟性を得ることができますが、型の安全性が失われるリスクがあります。any型の使用は極力避けるべきです。
例えば、以下のようにany型を使用すると、同じ変数が異なる種類のデータを受け入れることができます。
let anything: any = 4; // 最初は数値
anything = "hello"; // 文字列に変更可能
anything = false; // ブーリアン(真偽値)に変更可能この例では、anythingという変数が最初に数値型のデータを持ち、次に文字列型、ブーリアン型のデータに変更されています。any型を使うと、一つの変数でさまざまな型のデータを扱うことが可能になります。しかし、型の不一致によるエラーを見逃すリスクがあるため、注意が必要です。
関数
TypeScriptでの「関数」の定義とは、関数が受け取る引数(パラメータ)と、関数から返される値(戻り値)の型を明確に指定することです。関数がどのようなデータを扱うかがはっきりとし、誤った型のデータが渡されるのを防ぎます。
例えば、以下のような関数を考えてみましょう。
function add(x: number, y: number): number {
return x + y;
}add関数は、2つの数値型の引数xとyを受け取り、和を数値型の戻り値として返します。
また、戻り値がない関数の場合、戻り値の型としてvoidを使います。例えば、メッセージをログに出力するだけの関数は次のようになります。
function logMessage(message: string): void {
console.log(message);
}logMessage関数は文字列型の引数を受け取りますが、戻り値はありません。
関数の引数がオプショナル(任意)である場合、引数名の後に?を付けて指定します。例えば、あいさつをカスタマイズできる関数は次のようになります。
function greet(name: string, greeting?: string): string {
return greeting ? `${greeting}, ${name}` : `Hello, ${name}`;
}greet関数は、必須のname引数とオプショナルなgreeting引数を受け取ります。
さらに、TypeScriptではJavaScriptのアロー関数も型定義できます。例えば、2つの数値を掛け合わせる関数は次のように書けます。
const multiply = (a: number, b: number): number => {
return a * b;
};multiplyアロー関数は、2つの数値型の引数を取り、数値型の戻り値を返します。
TypeScriptで関数の型を定義することにより、コードの意図が明確になり、型の安全性が向上します。関数に誤った型の引数が渡されることを防止できるのです。
TypeScriptの基本的な型の機能
TypeScriptでは、型の機能を利用して、より安全で読みやすいコードを記述できます。型推論や型アサーションなどの機能は、開発者が効率的にコードを管理し、エラーを減らすのに役立ちます。ここでは、TypeScriptの基本的な型の機能を説明します。
型推論
型推論は、TypeScriptが自動的に変数の型を決定する機能です。型を明示的に宣言しない場合、TypeScriptは代入された値に基づいて変数の型を推論します。
例えば、let number = 5;
(型推論を使わない場合は「let number: number = 5;」)
と記述すると、numberは自動的にnumber型と推論されます。型推論は、コードを短くし、可読性を高めるのに役立ちます。
型アサーション
型アサーションは、開発者がTypeScriptに特定の型を「断言」する方法です。開発者がその変数の型についてTypeScriptよりも詳しいときに使用されます。
例えば、
let someValue: any = "this is a string";
let strLength: number = (<string>someValue).length;と記述することで、someValueが文字列であることをTypeScriptに伝え、lengthプロパティを安全に使用できます。型アサーションは、型情報が不足している場合に有用です。
// 型アサーションを使わない記述:
let someValue: string = "this is a string";
let strLength: number = someValue.length;型エイリアス
型エイリアスとは、特定の型に新しい名前を付ける方法です。型エイリアスは、コードをより読みやすくするために使われます。既にある型に別の名前をつけて、その型をよりわかりやすく表現することです。
たとえば、TypeScriptでは以下のように型エイリアスを定義できます。
type StringOrNumber = string | number;このコードでは、「StringOrNumber」という新しい型を作っています。この型は、「string」(文字列)または「number」(数値)のいずれかを意味します。つまり、「StringOrNumber」型の変数は、文字列か数値のどちらかを含むことができるということです。
型エイリアスを使う主な利点は、複雑な型を簡単に表現できることです。型エイリアスにより、コードの再利用が簡単になり、プログラム全体の可読性が向上します。また、コードを変更する際にも柔軟性が増します。
インターフェース
インターフェースとは、オブジェクトがどのような形をしているべきかを定義する方法です。「オブジェクト」とは、プログラミングにおいて様々なデータを一つにまとめたものです。例えば、従業員の名前や年齢などの情報をまとめたものがオブジェクトです。
インターフェースを使うと、オブジェクトが持つべき情報(プロパティ)と、それぞれの情報の型を指定できます。インターフェースにより、オブジェクトの形状が明確になり、そのオブジェクトがどのような情報を含むべきかがわかりやすくなります。
例えば、以下のようにインターフェースを定義できます。
interface User {
name: string;
age: number;
}この例では、「User」というインターフェースを作成しています。Userインターフェースは、「name」と「age」という二つのプロパティを持つことが定義されています。「name」は文字列型、「age」は数値型であると指定されています。
インターフェースを使用する主な利点は、オブジェクトがどのような構造を持つべきかを明確にし、プログラム内での一貫性を保証することです。インターフェースにより、誤った型や不足しているプロパティの使用を防ぎ、より安全で整理されたコードを書くことができます。
クラス
クラスは、オブジェクトの「設計図」として機能します。「オブジェクト」は、さまざまなデータや機能を一つにまとめたものです。たとえば、人の名前や年齢などの情報を持つ「人」というオブジェクトが考えられます。
クラスを使うと、オブジェクトの構造や振る舞いを定義できます。また、クラスはオブジェクト指向プログラミングの主要な概念である継承(既存のクラスから新しいクラスを作成する)、カプセル化(データや機能を一つにまとめる)、多様性(異なるオブジェクトを同じように扱う)などをサポートします。
- 継承: あるクラスの特性を別のクラスが受け継ぐ
- カプセル化: オブジェクトの詳細な内部情報を隠し、外部からのアクセスを制限する
- 多様性: 異なるクラスのオブジェクトが同じ方法で使用できる
TypeScriptでは、JavaScriptのクラス構文に型を追加できます。
例えば、以下のようなクラスを作成できます。
class Person {
name: string;
constructor(name: string) {
this.name = name;
}
}この例では、「Person」というクラスを作成しており、「name」というプロパティ(情報)が含まれています。constructorという特別なメソッド(関数)は、新しい「Person」オブジェクトが作られるときにnameプロパティを初期化するために使われます。
クラスを使用する主な利点は、コードの構造を明確にし、コードの再利用性とメンテナンス性を向上させることです。プログラムが大規模になっても管理しやすくなり、同じ種類のオブジェクトを簡単に何度も作成できます。
TypeScriptの開発で重要な型
Enum型
「Enum型(列挙型)」とは、限られた選択肢(固定された値の集合)を管理するのに役立つ方法です。
Enum型を使うと、特定の値に名前を付けて、一つのグループとして扱うことができます。例えば曜日や月の名前など、限られた数の選択肢がある場合に便利です。
以下のコードは、曜日をEnum型で定義しています。
enum Days {
Sunday,
Monday,
Tuesday,
Wednesday,
Thursday,
Friday,
Saturday,
}上記のコードは、曜日に関連する操作が簡単かつエラーの少ない方法で行えます。Enum型を使用すると、特定の値のセットに対して名前を付けて管理できるため、コードの意図が明確になり、エラーの可能性を減らします。
ジェネリック型
「ジェネリック型」とは、コードの再利用性を高める方法です。ジェネリック型を使うと、さまざまな種類のデータで機能する汎用的なコードを作成できます。一般的にプログラムを書くときには、その機能が扱うデータの種類(例えば、数値、文字列など)を指定する必要があります。しかし、ジェネリック型を使うと、具体的なデータの種類にこだわらずに、一つの機能をさまざまな種類のデータで使えます。
以下の関数は、ジェネリック型を使用しています。
function identity<T>(arg: T): T {
return arg;
}identity関数は、任意の型Tの値を受け取り、同じ型の値を返します。ここでのTは、実際に関数を使う時に決まる型を表しています。この関数は数値で使うことも、文字列で使うことも、他のどんな型のデータで使うこともできるということです。
ジェネリック型の利点は、コードをより柔軟にしながらも、型の安全性を保つ点です。特に大規模なアプリケーションやライブラリで、コードの再利用が容易になり、より効率的かつ安全なプログラミングが可能になります。
Union型とIntersection型
Union型とIntersection型は、TypeScriptで使われる、柔軟なデータの型を定義する方法です。
Union型は、「または」という意味です。例えば、number | stringと書くと、「数値または文字列」という意味になります。データが数値か文字列のどちらか一方であることを示します。
Intersection型は、「かつ」という意味です。
Union型とIntersection型の例を見てみましょう。
type Employee = {
name: string;
startDate: Date;
};
type Admin = {
name: string;
privileges: string[];
};
type ElevatedEmployee = Employee & Admin; // Intersection型この例では、ElevatedEmployeeという新しい型を作っています。Employee(従業員の情報)とAdmin(管理者権限の情報)の両方の特徴を持ち合わせています。つまり、ElevatedEmployeeは従業員の情報と管理者の権限の両方を持つということです。
Union型とIntersection型を上手く使うと、データの形を柔軟かつ明確に定義でき、TypeScriptの強力な型システムをフル活用できます。
リテラル型
リテラル型は、特定の固定された値(文字列や数値など)を「型」として指定する方法です。
リテラルの英語の綴りは “literal” です。日本語での意味は「文字通り」や「直接的な」という意味になります。プログラミングの文脈では、プログラムのコード内で直接指定された固定値を指し、変数や計算式などではない、そのままの値そのもののことです。
リテラル型により、特定の値しか受け入れない変数や関数の引数を作成できます。プログラムの意図をよりはっきりさせ、間違いを減らすのに役立ちます。
リテラル型の例を見てみましょう。
type Direction = "up" | "down" | "left" | "right"; // リテラル型この例では、「Direction」という型を定義しています。この型は、”up”、”down”、”left”、”right”という4つの文字列のいずれかのみを受け入れます。プログラムがこれらの値以外のものを扱おうとしたときに、エラーが発生して、間違いを防ぐことができます。
リテラル型は、プログラムに「この変数はこの特定の値しか使えない」という厳格なルールを設ける方法です。リテラル型により、プログラムを期待通りに動作させるのに役立ちます。
never型
never型とは、特定の変数や関数が決して通常の値を持たないことを示す方法です。never型は、プログラムがエラーによって停止したり、終わらないループに陥ったりする場合に使われます。
例えば、以下の関数を見てみましょう。
function error(message: string): never {
throw new Error(message);
}この関数はエラーメッセージを受け取り、プログラムをエラーで停止させます。この関数は通常の方法で終了せず、エラーを発生させるため、戻り値の型は never とされます。つまり、この関数は決して通常の値を返さないことが明示されています。
never型は、プログラムの振る舞いをより正確に表現するために使われ、誤って正常な値を返すことを防ぎます。never型は、プログラムの安全性を高める一つの方法です。
TypeScriptのテクニック
Optional Chaining
Optional Chaining(オプショナルチェイニング)は、オブジェクトのプロパティにアクセスする際に、そのプロパティが存在しなくてもエラーを起こさずに処理を進めることです。「?」という特別な記号を使って、あるオブジェクト(データの集まり)のプロパティ(特定のデータ)にアクセスする際、そのプロパティが実際に存在しなくてもエラーを起こさずに済むようにするものです。Optional Chainingにより、より安全にオブジェクトの深い部分にアクセスでき、コードが読みやすく、安全になります。
例えば、以下のような場合を考えてみましょう。
interface User {
name: string;
details?: {
age: number;
address?: {
street: string;
};
};
}
const user: User = { name: "Alice", details: { age: 30 } };
console.log(user.details?.address?.street); // undefined, エラーなしこの例では、userというオブジェクトのdetailsプロパティやその中のaddressプロパティが存在しない場合でも、エラーが発生せずundefinedが返されます。
Non-null Assertion Operator
Non-null Assertion Operator(非 null アサーション演算子)は、「!」という記号を使って、特定の値が絶対にnullやundefined(値がない状態)でないことをプログラムに教えるために使います。Non-null Assertion Operatorは、開発者がその値が絶対にnullやundefinedでないと確信している場合に便利ですが、誤った使用はエラーの原因になるため、注意が必要です。
const myElement = document.getElementById("myElement")!;このコードでは、getElementByIdの結果がnullでないという確信があるため、「!」を使用しています。しかし、本当にその値がnullやundefinedでないという確信がなければ、「!」記号は使わない方が良いでしょう。
型ガード
型ガードは、変数がどのような型であるかを確認し、その型に応じて正しい処理をする方法です。型ガードによって、変数が特定の型(たとえば数値や文字列など)であることを確認し、その型に応じて適切な処理を行います。型ガードにより、実行時に変数の型が正しいことを保証し、エラーを防ぐことができます。
例を見てみましょう。
function isNumber(value: any): value is number {
return typeof value === "number";
}
function doSomething(value: number | string) {
if (isNumber(value)) {
console.log(value.toFixed(2)); // 数値の処理
} else {
console.log(value.toUpperCase()); // 文字列の処理
}
}この例では、「isNumber」という関数が型ガードとして機能しています。この関数は、引数として渡されたvalueが数値かどうかをチェックします。doSomething関数内では、isNumberを使ってvalueが数値かどうかを確認し、数値であれば数値に対する処理(小数点以下2桁までの数値に丸める)を、文字列であれば文字列に対する処理(大文字に変換する)を行います。
型ガードは、変数がどのような型であるかを確認し、その型に応じて正しい処理をするための安全な方法です。
keyofオペレーター
keyofオペレーターは、オブジェクトのキーをまとめて取り出し、それを新しい型として使うツールです。keyofオペレーターを使用すると、オブジェクトのキーに基づいて、動的に新しい型を作成できます。
例えば、以下のような場合を考えてみましょう。
interface User {
name: string;
age: number;
}
type UserKeys = keyof User; // "name" | "age"この例では、「User」というインターフェース(オブジェクトの構造を定義するもの)があり、「name」と「age」という二つのキーがあります。keyof Userを使うことで、「UserKeys」という新しい型が作成され、「”name” | “age”」という形式になります。つまり、「UserKeys」は「User」のすべてのキーの集合として定義されます。
keyofオペレーターにより、プログラムを柔軟かつ効率的な記述が可能になります。
インデックス型
インデックス型は、オブジェクトのプロパティ(オブジェクト内の各要素)にアクセスするための型を定義する方法です。インデックス型を使うことで、キーが異なっても、それぞれのキーに割り当てられる値の型を統一できます。インデックス型により、プログラムを柔軟かつ効率的な記述が可能になります。
例を見てみましょう。
interface StringDictionary {
[index: string]: string;
}
const myDict: StringDictionary = {
hello: "world",
name: "Alice"
};この例では、「StringDictionary」というインターフェース(オブジェクトの構造を定義するもの)を定義しています。このインターフェースでは、どんな文字列のキーにも、文字列型の値を持つことができるように設定されています。例えば、myDictというオブジェクトを作成する際には、helloとnameという異なるキーを持っていますが、それぞれのキーの値は文字列(”world”と”Alice”)です。
インデックス型は、異なる名前のキー(プロパティ名)に対して、同じ型の値を持つオブジェクトを作成する際に役立ちます。
readonly
readonlyは、オブジェクトの特定のプロパティを「変更不可」として設定する機能です。readonlyを使うと、そのプロパティに一度値が割り当てられた後、その値を変更できなくなります。readonlyにより、プログラムの安定性が高まります。readonlyはオブジェクトの一貫性を保持し、意図しない変更を防ぐのです。
例を見てみましょう。
interface User {
readonly id: number;
name: string;
}
const user: User = { id: 1, name: "Alice" };
user.name = "Bob"; // OK
user.id = 2; // エラー: 'id' は readonly なので変更できませんこの例では、Userというインターフェース(オブジェクトの構造を定義するもの)にidというreadonlyプロパティがあります。userオブジェクトが作成された後、nameプロパティを変更することは可能ですが、idプロパティは読み取り専用なので、一度設定された後にその値を変更しようとするとエラーが発生します。
unknown
unknown型は、TypeScriptで最も安全な任意の値を表す型です。any型とは異なり、unknown型の変数に対しては、具体的な型が確認されるまで、任意の操作を行うことができません。unknownによって、型の安全性が高まります。
function safeFunction(input: unknown) {
if (typeof input === "string") {
console.log(input.toUpperCase()); // OK
} else if (typeof input === "number") {
console.log(input.toFixed(2)); // OK
}
}
safeFunction("hello"); // OK
safeFunction(42); // OK
safeFunction(true); // 何もしないこの例では、safeFunction は unknown型の引数を受け取ります。具体的な型チェックを行うことで、入力が文字列または数値である場合にのみ、特定の操作を実行します。不明な型の値を安全に扱うことができます。
非同期のAsync/Await
非同期処理とは、プログラムがある作業を待ちながら他の作業を進めることができるようにする処理のことです。TypeScriptでは、asyncとawaitという二つのキーワードを使って、非同期処理をより簡単かつ直感的に書くことができます。
asyncキーワード:asyncを関数の前に付けると、その関数は「非同期関数」となり、常に「Promise」という特殊なオブジェクトを返します。Promiseは、非同期処理が完了した後の結果を扱うためのオブジェクトです。awaitキーワード:awaitは、非同期処理が完了するのを待つために使います。awaitにより、非同期処理が終わるまで次のコードの実行を一時停止し、処理が終わったら再開します。
例を見てみましょう。
async function fetchData(url: string): Promise<string> {
const response = await fetch(url); // ウェブからデータを取得
const data = await response.text(); // 取得したデータをテキストに変換
return data; // テキストデータを返す
}
fetchData("https://example.com").then(data => console.log(data));この例では、fetchData関数はウェブからデータを非同期で取得し、そのデータをテキストとして返します。awaitを使って、ウェブからデータを取得する処理と、データをテキストに変換する処理が完了するのを待っています。非同期コードが、通常の同期コードのように読みやすくなります。
型定義ファイル
TypeScriptでは、.d.tsという拡張子を持つ特別なファイル(型定義ファイル)を使って、JavaScriptライブラリの型情報を提供できます。型定義ファイルにより、TypeScriptプロジェクトでJavaScriptライブラリを型の安全性を保ちながら使用できます。
型定義ファイルでは、declare moduleというキーワードを使って、特定のライブラリやモジュールのための型定義を行います。型定義ファイルには、ライブラリが提供する関数や変数などの型情報が含まれます。
例を見てみましょう。
// example.d.ts
declare module 'example' {
export function exampleFunction(param: string): number;
}この例では、「example」という名前のモジュール(JavaScriptライブラリの一部)の型定義を行っています。exampleFunctionという関数が文字列をパラメータとして受け取り、数値を返すことを定義しています。
型定義ファイルを作成すると、TypeScriptコンパイラはexampleモジュールについての型情報を理解し、モジュールを使用する際に適切な型チェックを行います。型定義ファイルにより、プログラムの安全性と正確性が向上します。
TypeScriptの開発時設定
tsconfig.json
TypeScriptプロジェクトでは、「tsconfig.json」というファイルを使用して、コンパイラ(TypeScriptコードをJavaScriptコードに変換するプログラム)の設定を管理します。tsconfig.jsonファイルには、出力されるファイルがどこに保存されるか、どのバージョンのJavaScriptを対象とするか、どのようなモジュールシステムを使用するかなど、多くの重要な設定が含まれています。
例えば、以下のような設定があります。
{
"compilerOptions": {
"target": "es5",
"module": "commonjs",
"strict": true,
"outDir": "./dist"
}
}この設定では、以下のことが指定されています。
"target": "es5":TypeScriptコードをECMAScript 5(JavaScriptの古いバージョン)に変換する。"module": "commonjs":CommonJSというモジュールシステムを使用する。"strict": true:より厳密な型チェックを行う。"outDir": "./dist":出力されるJavaScriptファイルをdistというディレクトリに保存する。
tsconfig.jsonは、TypeScriptプロジェクトの振る舞いを細かく制御する重要な設定ファイルです。tsconfig.jsonにより、プロジェクトの設定を一箇所で管理し、開発の効率を向上させます。
Prettier
Prettierは、コードの書式を自動的に整えるツールです。TypeScriptプロジェクトにPrettierを導入すると、プロジェクト全体で統一されたコーディングスタイルを維持できます。Prettierによって、読みやすくメンテナンスしやすいコードを保つことが可能になります。通常、Prettierはコードを保存する際に自動的に書式を整えるように設定されます。
例えば、以下のようなPrettierの設定があります。
{
"semi": false,
"singleQuote": true,
"printWidth": 80
}この設定では、以下のルールが適用されます。
"semi": false:行の終わりのセミコロン(;)を省略する。"singleQuote": true:ダブルクォート(” “)ではなく、シングルクォート(’ ‘)を文字列の囲みに使用する。"printWidth": 80:行の最大幅を80文字に制限する。
Prettierを使用することで、開発者間でのスタイルの違いを減らし、コードレビューの効率を向上させます。コードの品質を維持しやすくなり、チームでの開発がスムーズに進められます。
TypeScriptの開発時設定
ESLint
ESLintは、TypeScriptで書かれたコードの品質をチェックするために使われます。ESLintは、コードが一定の基準に従って書かれているかどうかを分析し、間違いや将来問題になりそうな点を早めに見つけるのに役立ちます。ESLintは、使う人が自分の好みや必要に合わせて設定を変更できるのも特徴です。
{
"extends": ["eslint:recommended", "plugin:@typescript-eslint/recommended"],
"parser": "@typescript-eslint/parser",
"plugins": ["@typescript-eslint"],
"rules": {
"no-unused-vars": "warn",
"no-console": "off"
}
}上記の設定では、TypeScriptのための推奨されるルール(プログラミングのガイドライン)に従い、プログラムに使われていない変数があったら警告を出すように設定されています。さらに、この設定では「no-console」というルールをオフにしているので、プログラム内でコンソール(コンピュータの画面にメッセージを出力する機能)を使うことが許可されています。ESLintは、プログラマがより良いコードを書くためのサポートをするツールです。
コンパイルオプション
TypeScriptは、通常JavaScriptに変換されてから使われます。この変換過程を「コンパイル」と呼びます。TypeScriptでコンパイルを行う際には、「tsconfig.json」というファイルを使って、どのように変換するかを細かく設定できます。これを「コンパイルオプション」と言います。
たとえば、どのバージョンのJavaScriptに変換するか、コードのどの部分をどのように扱うか(モジュールシステム)、コードの型に関する厳密さなど、多くの設定が可能です。
{
"compilerOptions": {
"target": "es5",
"module": "commonjs",
"strict": true,
"esModuleInterop": true,
"skipLibCheck": true
}
}上記の設定では、古いバージョンのJavaScript(es5)に変換し、特定のモジュールシステム(commonjs)を使用するようにしています。また、型チェックをより厳格にする設定や、特定の互換性を高めるための設定も含まれています。さらに、ビルド時間を短縮するために一部のチェックを省略する設定もあります。
これらのオプションを通じて、プログラマは自分のプロジェクトのニーズに合わせて、最適なコンパイル環境を作ることができます。
Reactの基礎
Reactの基礎
Reactは、コンポーネントベースのライブラリで、インタラクティブなウェブアプリケーションの開発に適しています。コンポーネントとは、「部品」のことです。Reactは、状態管理、ライフサイクルメソッド、フックなどの機能を提供し、効率的なUI開発を可能にします。Reactはシンプルなコンセプトに基づいており、コンポーネント(=部品)の組み合わせで複雑なアプリケーションを構築できます。
Reactの始め方
Reactプロジェクトを始めるには、Node.jsがインストールされている必要があります。最も一般的な方法は、Create React Appを使うことです。Reactのプロジェクトテンプレートを提供し、初期設定を簡単にします。
npx create-react-app my-app
cd my-app
npm start上記のコマンドは新しいReactプロジェクトを作成し、ローカルサーバーでアプリケーションを起動します。ブラウザで localhost:3000 にアクセスすることで、Reactアプリケーションを確認できます。
なお、TypeScriptを使用する場合は、
create-react-app my-app --template typescript を実行します。
Reactの基礎
Reactの基本
Reactは、ウェブサイトやアプリの見た目や操作感(ユーザーインターフェース)を作るためのツールです。ReactはJavaScriptというプログラミング言語で作られていて、「コンポーネント」という小さな部品を組み合わせて、大きなアプリケーションを構築するのが特徴です。各コンポーネントは独立していて、何度も使い回すことができます。
Reactの特徴の一つに「宣言的なUI記述」があります。宣言的なUI記述とは、アプリケーションの現在の状態に基づいて、UI(ユーザーインターフェース)が自動的に更新されることです。開発者は、UIがどのように見えるべきかを指定するだけでよく、状態を管理する手間が省けます。
Reactのコンポーネントを作成する
Reactコンポーネント(=部品)は、関数(function)やクラス(class)を使って作ることができます。各コンポーネントはHTML要素を返す関数のようなもので、外部からデータを受け取ることができます(このデータは「props(プロパティ)」と呼ばれます)。
function Welcome(props) {
return <h1>Hello, {props.name}</h1>;
}
class Welcome extends React.Component {
render() {
return <h1>Hello, {this.props.name}</h1>;
}
}上記の例は、Welcomeコンポーネントが「Hello, [名前]」というメッセージを表示する簡単なコンポーネントです。関数とクラスの二つの方法で作ることができ、どちらも外部から受け取った名前(props.name)を使ってメッセージを表示します。各コンポーネントは他のReactコンポーネントの中で使われ、より複雑なユーザーインターフェースを構築する際に再利用されます。
Reactにおけるコンポーネント
React要素
Reactにおけるコンポーネントとは、ウェブサイトやアプリのユーザーインターフェースの構築に使われる小さな部品のことです。Reactでは、コンポーネントを使って、ウェブページやアプリの見た目や機能を作ります。
「React要素」とは、Reactアプリケーションの最も基本的な単位で、HTMLタグ(例えば、テキストや画像を表示するためのコード)のようなものです。React要素は一度作成すると変更できない不変のもので、Helloのように記述されます。
コンポーネント (Reactコンポーネント)
コンポーネントは、React要素を返すJavaScriptの関数またはクラスです。コンポーネントは独立しており、再利用が可能です。それぞれのコンポーネントは、見た目や動作を含めた一つのまとまりとして機能します。
関数コンポーネントは、最もシンプルな形式のコンポーネントで、外部からデータ(propsと呼ばれる)を受け取り、それを使ってReact要素(UIの一部)を作ります。
function Welcome(props) {
return <h1>Hello, {props.name}</h1>;
}この例は、Welcomeコンポーネントは外部から受け取った名前(props.name)を使って「Hello, [名前]」というメッセージを表示するコンポーネントです。
クラスコンポーネントは少し複雑で、状態管理(コンポーネントの情報の保存や変更)やライフサイクルメソッド(コンポーネントの作成や更新、削除時の特定の動作)といった機能を使うことができます。
class Welcome extends React.Component {
render() {
return <h1>Hello, {this.props.name}</h1>;
}
}Reactコンポーネントは、アプリケーションを構成する中心的な要素であり、「ビルディングブロック」として機能します。Reactコンポーネントを組み合わせて、大きな機能やUIを作り出します。
Reactにおける型
TypeScriptの型の定義とReactにおける型
ReactとTypeScriptを組み合わせることで、ウェブサイトやアプリのUIを作る際に、より安全で予測可能なコードを書くことが可能になります。
TypeScriptは、プログラミングの際に変数や関数の「型」を厳密に定義する言語の一つです。型とは、変数や関数がどのようなデータを扱うかを指定するもので、例えば数字や文字列などがあります。
ReactでTypeScriptを使用すると、コンポーネント(ウェブページやアプリの構成要素)のプロパティ(コンポーネントに与える情報)、状態(コンポーネントの現在の状況や情報)、イベントハンドラ(ユーザーの操作に応じた動作)などの型を正確に定義できます。
型を正確に定義することにより、開発者は予期しないエラーを減らし、より確実に動作するアプリケーションを制作できます。
例えば、以下のコードでは「WelcomeProps」という名前の型を定義しています。これは、Welcomeコンポーネントに「name」というプロパティが文字列であることを保証するものです。このように型を定義することで、コンポーネントが期待するデータの形を明確にし、間違った型のデータが入ることを防ぎます。
interface WelcomeProps {
name: string;
}
const Welcome: React.FC<WelcomeProps> = (props) => {
return <h1>Hello, {props.name}</h1>;
};また、Reactの「フック」と呼ばれる機能も、TypeScriptの型定義を利用して状態やコンテキスト(コンポーネント間で共有される情報)の型を指定できます。フックにより、Reactの機能をより安全かつ効果的に使うことができます。
TypeScriptとReactを組み合わせることで、開発者はReactの柔軟性と表現力を保ちつつ、型の安全性を確保できるのです。
Context
ReactのContext機能
ReactのContext機能は、コンポーネントツリーを通じてデータを効果的に渡す手段を提供します。プロップスのドリリング(子コンポーネントへのプロップスの連鎖的な渡し)を避けることが可能になります。
例えば、ある大きなレストランがあり、地下の厨房スタッフが最上階にある客室のウェイターにメッセージを伝えたいとします。通常、メッセージは地下から一階、二階、最上階へ、階を一つずつ経由して伝えられます。しかし、これには少し時間がかかります。もしレストランに「内線電話」があれば、厨房スタッフは直接最上階のウェイターにメッセージを伝えることができます。
ReactのContextは、この「内線電話」のようなものです。Reactで作られたアプリケーションでは、通常、情報(メッセージ)は親コンポーネント(地下の厨房)から子コンポーネント(一階、二階、最上階の客室)へと一つずつ渡されます。しかし、Contextを使うと、連鎖的な渡し方をせずに、直接必要なコンポーネント(最上階のウェイター)に情報を届けることができるのです。Contextにより、アプリケーションの情報伝達がより効率的かつ簡単になります。
ユーザーの設定やテーマ情報など、多くのコンポーネントで共有されるべき情報をContextで管理できます。
以下のコードでは、ユーザー設定をContextで作成し、提供しています。
// UserSettingsContextの作成
const UserSettingsContext = React.createContext();
// コンテキストプロバイダー
const UserSettingsProvider = ({ children }) => {
const [userSettings, setUserSettings] = useState({ theme: 'light' });
return (
<UserSettingsContext.Provider value={{ userSettings, setUserSettings }}>
{children}
</UserSettingsContext.Provider>
);
};
// コンテキストを使用するコンポーネント
const ThemeComponent = () => {
const { userSettings } = useContext(UserSettingsContext);
return <div>現在のテーマ: {userSettings.theme}</div>;
};Contextを使用することで、コンポーネント間での状態の共有がスムーズに行われ、コードの可読性と再利用性が向上します。
React Hooks (フック)
Reactのフック機能
Reactの「フック機能」は、ウェブサイトやアプリのインターフェースを作る際に使うツールです。特に、「関数コンポーネント」と呼ばれる小さなプログラムの部品の中で、その部品が持つデータ(状態)や、その部品の生まれたり消えたりする過程(ライフサイクル)を扱うために使われます。
React Hooksは、レストランの厨房の引き出しにある道具のようなものです。料理を作るときにさまざまな道具(フライパン、ボウル、スパチュラなど)を使います。それぞれの道具は特定の機能や目的に合わせて作られています。例えば、フライパンで炒め物を作ったり、ボウルで材料を混ぜたりします。
Reactでは、アプリケーションを「料理」と考えることができます。React Hooksは、料理を作る際に必要な「道具」です。それぞれのHook(例:useStateやuseEffect)は、特定の機能や目的に合わせて使われます。useStateは材料(アプリケーションの状態)を管理するためのもので、useEffectは特定の作業(例えば、料理が完成したらタイマーを止めるなど)を行うためのものです。
また、自分だけの特別な料理を作りたい場合、自分でカスタムの道具(カスタムフック)を作ることもできます。カスタムフックにより、アプリケーション(料理)がより柔軟かつ効率的に作られます。React Hooksは、関数コンポーネント(簡単な料理レシピ)をより強力で便利にするためのツールです。
useStateはコンポーネント内での状態管理を、useEffectはコンポーネントのライフサイクルに合わせた副作用の実行を可能にします。
以下はuseStateとuseEffectの基本的な使用例です。
const Counter = () => {
const [count, setCount] = useState(0);
useEffect(() => {
document.title = `現在のカウント: ${count}`;
}, [count]);
return (
<div>
現在のカウント: {count}
<button onClick={() => setCount(count + 1)}>増加</button>
</div>
);
};React Hooksはコードの再利用性と分離を促進し、関数コンポーネントをより強力で柔軟にします。
TypeScriptの基本的な型の機能とReact Hooks
TypeScriptとReactフックの組み合わせ
TypeScriptをReactのフック機能と組み合わせることで、プログラムのデータ(状態)の管理や、プログラムの動作に伴う追加的な効果(副作用)をより安全に扱うことができます。「副作用」とは、プログラミングの世界でよく使われる言葉で、コンポーネントの主な動作以外の追加的な動作や影響のことです。例えば、データの取得や保存などが「副作用」に該当します。
TypeScriptを使用することで、特にReactの「useState」というフックを使う際に、その状態が取りうる値の型を明確に指定できます。誤った型のデータが使用されることを防ぎ、プログラムの予期しない挙動やエラーを減らします。
const Counter: React.FC = () => {
const [count, setCount] = useState<number>(0);
return (
<div>
現在のカウント: {count}
<button onClick={() => setCount(count + 1)}>増加</button>
</div>
);
};上記のコードでは「useState(0)」としています。「count」という状態が数値型であることを明示しており、数値しか取らないことが保証されています。ボタンをクリックすることで数値が増加するという簡単なカウンター機能を安全に実装できます。
TypeScriptとReactフックを組み合わせることで、アプリケーションのデータ管理や動作の副作用をより安全かつ正確に扱うことができ、Reactアプリケーションの全体的な信頼性が高まるのです。
useStateとuseReducer
ReactフックのuseStateとuseReducer
Reactの「useState」と「useReducer」というフックは、ウェブサイトやアプリの特定の部分(コンポーネント)が持つデータ(状態)を管理するツールです。
「useState」は簡単なデータの管理に適しています。例えば、ある数字を表示し、ボタンを押すことでその数字を増やすような場合に使われます。
以下のコード例では、カウンターの数字(count)を管理しており、ボタンをクリックするたびに数値が1ずつ増えます。
const Counter = () => {
const [count, setCount] = useState(0);
return (
<div>
カウント: {count}
<button onClick={() => setCount(count + 1)}>増加</button>
</div>
);
};「useReducer」はもう少し複雑なデータの管理や、現在のデータに基づいて次のデータを決めるような場合に適しています。useReducerを使うと、アクション(何をするかを示す命令)に基づいて状態がどのように変化するかを指定する「reducer」関数を定義します。カウンターの例では、’increment’というアクションを受け取ると、カウントの数値を1増やします。
const counterReducer = (state, action) => {
switch (action.type) {
case 'increment':
return { count: state.count + 1 };
default:
return state;
}
};
const Counter = () => {
const [state, dispatch] = useReducer(counterReducer, { count: 0 });
return (
<div>
カウント: {state.count}
<button onClick={() => dispatch({ type: 'increment' })}>増加</button>
</div>
);
};useStateは単純な状態の管理に、useReducerはより複雑な状態の変更やロジックが必要な場合に適しています。どちらもReactのコンポーネントが持つデータを効果的に管理する重要なツールです。
useCallbackとuseMemo
ReactフックのuseCallbackとuseMemo
Reactの「useCallback」と「useMemo」というフックは、ウェブサイトやアプリの性能を向上させるために使われるツールです。特に計算コストが高い(つまり、多くのリソースや時間を必要とする)処理を最適化するのに役立ちます。
「useCallback」は、関数のメモ化に使用されます。メモ化とは、ある関数の結果を記憶しておき、同じ入力があった場合には以前の計算結果を再利用することです。同じ計算を何度も繰り返さずに済むため、リソースの節約になります。useCallbackは、特定の依存関係が変わったときにのみ関数を再計算するように設定できます。
「useMemo」は、計算結果自体のメモ化に使われます。useCallbackと同様に、特定の入力に基づいた計算の結果を記憶し、入力が変わらない限りその結果を再利用します。同じ計算を何度も行うことなく、既に計算済みの結果を使うことができます。
useCallbackの例:
const memoizedCallback = useCallback(
() => {
// 高コストな計算や処理
},
[依存配列],
);useMemoの例:
const memoizedValue = useMemo(() => computeExpensiveValue(a, b), [a, b]);各フックは、不必要な再計算を防ぐことで、アプリケーションのパフォーマンスを向上させます。しかし、必要以上に使うと、かえってパフォーマンスが低下することもあるため、適切な使用が重要です。
useCallbackとuseMemoは、アプリケーションの動作をスムーズにし、効率的にするための便利なツールですが、使い方には注意が必要です。
useEffectとuseLayoutEffect
ReactフックのuseEffectとuseLayoutEffect
Reactの「useEffect」と「useLayoutEffect」というフックは、ウェブサイトやアプリの特定のコンポーネント(=部品)の動作に関連した追加的な処理(=副作用)を組み込むために使用されるツールです。
「useEffect」は、コンポーネントが画面に表示された(DOMが更新された)後に特定の処理を行うために使います。データの取得やイベントリスナー(ユーザーの操作を監視する機能)の設定など、一般的な副作用に適しています。また、useEffect内で設定した処理は、コンポーネントが画面から消えるときにクリーンアップ(不要になった処理を停止すること)されます。
「useLayoutEffect」は、画面の表示が更新される前に特定の処理を行うために使われます。画面のレイアウトに影響を与えるような処理に適しています。しかし、useLayoutEffectを使うとパフォーマンスに影響を与えることがあるため、必要な場合にのみ使用することが推奨されます。
useEffectの例:
useEffect(() => {
// 副作用のロジック
return () => {
// クリーンアップ
};
}, [依存配列]);useLayoutEffectの例:
useLayoutEffect(() => {
// DOMの更新前に実行される副作用
}, [依存配列]);useEffectとuseLayoutEffectは、コンポーネントのライフサイクル(生まれたり消えたりする過程)に合わせて追加的な処理を行うためのツールです。useEffectは一般的な処理に、useLayoutEffectはよりデリケートな画面レイアウトの処理に適していますが、使用する際にはパフォーマンスへの影響を考慮する必要があります。
useContext
ReactフックのuseContextの活用
useContextは、ReactのコンテキストAPIをフックとして使いやすくするものです。コンポーネントツリーを通してデータを伝達できます。例えば、テーマやローカライゼーション設定など、多くのコンポーネントで共有される値を管理するのに便利です。
useContextは、大きなレストランでスタッフが情報を共有する方法のようなものです。レストランには多くのセクション(コンポーネント)があり、それぞれのセクションで異なる業務が行われています。しかし、全てのセクションで共通の情報(例えば、予約件数や厨房の状況など)を共有する必要があります。
通常、このような情報はレストランの管理室でスタッフに配布され、個別に伝達されます。しかし、これだと非効率です。useContextは、共通の情報を掲示板に掲示するようなものです。どのセクションからでもその掲示板を見ることができ、必要な情報をすぐに手に入れることができます。
useContextは、Reactアプリケーション内で、テーマの設定や言語の選択など、多くのコンポーネントで共有されるべき情報を効率的に管理し、アクセスするための方法を提供します。useContextにより、情報の伝達がスムーズになり、開発の効率が向上します。
useContextの使用例:
const ThemeContext = React.createContext('light');
const App = () => {
return (
<ThemeContext.Provider value="dark">
<Toolbar />
</ThemeContext.Provider>
);
};
const Toolbar = () => {
return (
<div>
<ThemedButton />
</div>
);
};
const ThemedButton = () => {
const theme = useContext(ThemeContext);
return <button style={{ background: theme === 'dark' ? 'black' : 'white' }}>ボタン</button>;
};この例では、ThemeContextを通してアプリケーション全体でテーマを共有しています。useContextはコードをシンプルにし、プロップスのドリリング(親から子への値の伝達)を回避できます。
useRefとuseImperativeHandle
useRefとuseImperativeHandleの使い方
useRefはDOM要素にアクセスするために使用され、useImperativeHandleは子コンポーネントのインスタンス値を親コンポーネントに公開するために使用されます。
まずuseRefを考えてみましょう。useRefは、大きなレストランの中で特定のテーブルや料理を直接見つける方法のようなものです。レストランにはたくさんのテーブルや料理がありますが、useRefを使うと、大量の選択肢の中から特定のテーブルや料理(この場合はウェブページ上の特定の部分や要素)を直接指定して、すぐにアクセスできます。
次にuseImperativeHandleです。useImperativeHandleは、特定のシェフ(子コンポーネント)が持っている特別なレシピを、そのシェフが許可したマネージャー(親コンポーネント)だけに見せるようなものです。普通は秘密にされているレシピや調理方法を、特定の関係にある他のスタッフにだけ公開するために使われます。
useRefとuseImperativeHandleの機能は、Reactで作られたウェブアプリケーションにおいて、特定の部分に効率的にアクセスしたり(useRef)、特定の関係にあるコンポーネント間で情報を共有(useImperativeHandle)するために使われます。useRefとuseImperativeHandleにより、アプリケーションの操作や管理がより柔軟で効率的になります。
useRefとuseImperativeHandleの使用例
下記のコードでは、Reactの useRef と useImperativeHandle フックを使用しています。それぞれのフックの役割と使い方を説明します。
useRefの使用例:
useRef フックは、DOM要素への参照を作成し、それを管理するために使用されます。
const InputComponent = () => {
const inputRef = useRef(null);
const focusInput = () => {
inputRef.current.focus();
};
return (
<div>
<input ref={inputRef} type="text" />
<button onClick={focusInput}>フォーカス</button>
</div>
);
};useImperativeHandleの使用例:
useImperativeHandle は、子コンポーネントのインスタンス値を親コンポーネントに公開するために使用されます。
const FancyInput = React.forwardRef((props, ref) => {
const inputRef = useRef();
useImperativeHandle(ref, () => ({
focus: () => {
inputRef.current.focus();
}
}));
return <input ref={inputRef} {...props} />;
});
const ParentComponent = () => {
const fancyInputRef = useRef();
const focusInput = () => {
fancyInputRef.current.focus();
};
return (
<div>
<FancyInput ref={fancyInputRef} />
<button onClick={focusInput}>子コンポーネントのフォーカス</button>
</div>
);
};useRefはDOMへの参照を保持するのに使い、useImperativeHandleは子コンポーネントの特定の関数や値を親コンポーネントに公開するのに使用されます。
カスタムフックとuseDebugValue
カスタムフックの作成とuseDebugValueの利用
カスタムフックは、複数のフックやロジックを一つのフックにまとめて再利用するために使用されます。useDebugValueは、カスタムフックのデバッグを容易にするために使用されます。
まずカスタムフックについて考えてみましょう。カスタムフックは、よく使う料理のレシピを一つのレシピカードにまとめるようなものです。例えば、ある料理を作るときにいつも同じスパイスの組み合わせを使うとします。スパイスの組み合わせを毎回個別に用意する代わりに、一つの「スパイスミックス」としてまとめてしまえば、次回からはそのスパイスミックスを一回分使うだけで済み、料理が簡単になります。カスタムフックも同様に、よく使うコードのパーツを一つにまとめ、何度も再利用できます。
useDebugValueは、このレシピカードにメモを付け加えるようなものです。料理を作る際に、どのスパイスがどれだけ効いているかを知るためにメモを残すことができます。同様に、useDebugValueはカスタムフックの中で何が起こっているかを理解しやすくするためのメモやヒントを提供します。useDebugValueにより、問題が発生した時に原因を見つけやすくなります。
カスタムフックとuseDebugValueの機能は、Reactで作られたアプリケーションをより効率的に、そして問題を解決しやすくするために役立ちます。
カスタムフックの使用例:
const useCustomHook = () => {
const [value, setValue] = useState('');
// ビジネスロジックやフックの使用
return { value, setValue };
};
useDebugValueの使用例:
const useCustomHook = () => {
const [value, setValue] = useState('');
useDebugValue(value ? '値が設定されています' : '値が設定されていません');
// ビジネスロジックやフックの使用
return { value, setValue };
};カスタムフックはコードの再利用性を高め、useDebugValueはReact DevToolsでカスタムフックの状態を視覚的に確認できるようにします。
Next.jsの基礎
Next.jsは、ウェブサイトやアプリケーションを作るためのツールの一つで、Reactをベースにしています。Next.jsは特に、ウェブサイトのページをより速く、より効率的に表示するための高度な機能を提供します。
Next.jsの特徴の一つは、「サーバーサイドレンダリング」です。サーバーサイドレンダリングとは、ウェブページの内容がサーバー(インターネット上のコンピュータ)上で事前に生成されることです。サーバーサイドレンダリングにより、ウェブサイトを訪れた人がページをより速く見ることができます。
また、Next.jsでは「静的サイト生成」も可能です。ページの内容があらかじめ完全に生成され、必要に応じて素早く表示されるというものです。静的サイト生成により、ウェブサイトの速度が向上し、訪問者にとって快適な閲覧体験を提供できます。
Next.jsを使うと、SEO(検索エンジン最適化)の向上にも役立ちます。SEOは、ウェブサイトがGoogleなどの検索エンジンに適応することで、より多くの訪問者をウェブサイトに引き寄せます。
Next.jsは、ウェブサイトやアプリケーションを速く、効率的に、検索エンジンに優れた形で表示するための強力なツールです。
プロジェクトのセットアップ
Next.jsプロジェクトを開始するには、以下の手順を実行します。
Node.jsがインストールされていることを確認します。
コマンドラインで、npx create-next-app@latest
を実行して新しいプロジェクトを作成します。
作成したディレクトリに移動し、npm run devで開発サーバーを起動します。
npx create-next-app@latest <プロジェクト名>
cd my-next-app
npm run devこれで、localhost:3000でNext.jsアプリケーションが実行されます。
プロジェクトの基本的な構成
Next.jsプロジェクトは、大きなレストランのようなものです。レストランには様々なセクション(ディレクトリ)があり、それぞれのセクションは特定の役割を持っています。
- pages/: レストランの「各セクション」のようなものです。ここには異なるページ(ウェブサイトの異なるセクションや画面)があります。たとえば、レストランのキッチンが「調理エリア」となるように、
pages/about.jsはウェブサイトの/aboutのセクションになります。 - public/: 「エントランス」のような場所です。訪問者(ウェブサイトの訪問者)が見ることができる静的なファイル(画像、フォントなど)を置きます。
- components/: 「用具室」のような場所です。一般的にはウェブサイト全体で再利用される部品(ボタン、フォームなどのReactコンポーネント)を保管します。
- styles/: 「レストランのデコレーション部門」のようなものです。ウェブサイトの外観(色、レイアウトなど)に関するスタイルやCSSモジュールがあります。
- next.config.js: 「レストランの管理オフィス」のようなものです。レストラン(Next.jsプロジェクト)の全体的な設定やカスタマイズを行います。
Next.jsの便利な点は、各セクションへの「自動移動システム」が備わっていることです。開発者は各セクションへのルーティング(ページ間の移動)を自分で設計する必要がなく、自動的に処理されます。開発者は、より重要な部分に集中して作業を進めることができます。
Next.jsのレンダリング手法
Next.jsは、多様なレンダリング手法を提供し、アプリケーションのパフォーマンスとSEO対策を最適化します。
レンダリング手法とは、ウェブページがどのように作られてユーザーの画面上に表示されるかというプロセスのことです。
例えば、あなたがレストランでメニューを見て料理を選ぶとします。レンダリングは、あなたが注文した料理がキッチンで準備され、あなたのテーブルに運ばれてくるまでのプロセスに似ています。レンダリングのプロセスには、食材を準備すること、料理を調理すること、最終的に盛り付けて提供することなどが含まれます。
Next.jsでは、この「料理の準備と提供」のプロセスにいくつかの異なる方法があります。例えば、料理を予め準備しておく方法(静的サイト生成(SSG))、客のテーブルで料理を完成させる方法(クライアントサイドレンダリング(CSR))、注文があったときにその場で料理を作る方法(サーバーサイドレンダリング(SSR))などです。
レンダリングの異なる方法は、ウェブページがどれだけ早く読み込まれ、ユーザーに表示されるか、検索エンジンにどれだけ適しているか(SEO対策)など、ウェブサイトのパフォーマンスに影響を与えます。
Next.jsは、異なるレンダリング手法をサポートし、最適な方法でウェブサイトをユーザーに提供します。
ここでは、主なレンダリング手法について解説します。
静的サイト生成 (SSG)
静的サイト生成(SSG)は、料理を予め準備しておく方法と似ています。レストランが開店前にすべての料理を事前に準備し、客が注文した際には即座に提供するようなものです。
Next.jsを使用したSSGでは、ウェブサイトがビルドされる際にすべてのウェブページ(HTMLファイル)が事前に生成されます。このプロセスは、シェフがレストランの開店前にすべての料理を準備しておくことに相当します。その結果、ユーザーが特定のページをリクエストすると、すでに準備されているページが即座に表示されます。
SSGの利点は、ページロードの時間が大幅に削減され、ウェブサイトのパフォーマンスが向上することです。また、ウェブページが事前に準備されているため、アクセスピーク時でも迅速な処理が可能となり、全体の効率と顧客満足度が向上します。
Next.jsでは、getStaticPropsやgetStaticPathsを使ってSSGを実現します。
export async function getStaticProps() {
// 外部APIからデータを取得
const data = await fetchSomeData();
return { props: { data } };
}静的サイト生成 (SSG)は、内容が頻繁に変わらないウェブサイトや、訪問者に対して迅速なページ読み込みが求められる場合に適しています。例えば、会社のホームページやブログなど、一度作成されたら内容が頻繁に変わらないサイトに最適です。
クライアントサイドレンダリング (CSR)
クライアントサイドレンダリング(CSR)は、ブラウザでページの内容を動的に生成する手法です。CSRでは、ユーザーがページを訪れた時、サーバーからは基本的な枠組みだけが送られ、その後のページの内容(データや要素など)はブラウザで動的に生成されます。
CSRの利点は、ページの初期表示が速くなることです。サーバーから送信されるHTMLは最小限なので、ブラウザで表示されるまでの時間が短くなります。
CSRの欠点は、ページの表示に時間がかかる可能性があることです。ブラウザでページの内容を動的に生成するため、データの読み込みや処理に時間がかかることがあります。また、ユーザーの端末のスペックやネットワーク環境によって、表示速度が大きく変わる可能性があります。
function HomePage() {
const [data, setData] = useState(null);
useEffect(() => {
// データの動的取得
fetchSomeData().then(data => setData(data));
}, []);
return
{data ? renderData(data) : Loading…};
}
CSRは、ユーザーがページ上でさまざまな操作を行い、画面が頻繁に更新されるようなウェブアプリケーション(例えば、シングルページアプリケーション)に適しています。
サーバーサイドレンダリング (SSR)
サーバーサイドレンダリング(SSR)では、ユーザーがページを訪れた時、サーバー側でそのページの内容がリアルタイムで生成されます。生成されたページは直ちにユーザーに送信され、ブラウザで表示されます。
SSRの利点は、ページの表示が速く、最新の情報を提供できることです。サーバー側でページの内容を生成するため、データの読み込みや処理に時間がかかることはありません。また、ユーザーの端末のスペックやネットワーク環境に左右されません。
SSRの欠点は、ページの初期表示に時間がかかる可能性があることです。SSRでは、サーバー側でページの内容を生成するため、データの読み込みや処理に時間がかかることがあります。また、CSRと比べると、ページのサイズが大きくなる傾向があります。
export async function getServerSideProps(context) {
// データベースや外部APIからデータを取得
const data = await fetchData();
return { props: { data } };
}SSRは、常に最新の情報を表示する必要がある動的なウェブページに適しています。また、検索エンジン最適化(SEO)にも効果的です。ウェブページの内容がサーバー側で完全に構築されるため、検索エンジンがページの内容をより容易に理解できるからです。
インクリメンタル静的再生成 (ISR)
インクリメンタル静的再生成(ISR)は、Next.jsの特徴の一つで、ウェブサイトのページを作る方法の一つです。
ISRは、SSRとSSGの長所を組み合わせたものです。ISRを使うと、ウェブサイトのページは最初に一度生成され、その後一定の間隔でページが更新されて最新の状態を保ちます。たとえば、10秒ごとに特定のページを再生成し、最新の情報を提供する設定が可能です。
ISRにより、ウェブサイトは最新の内容を提供しつつ、ページの読み込みが速いという利点を維持します。頻繁に内容が更新されるウェブサイト(例えば、ブログやニュースサイト)に適しています。
export async function getStaticProps() {
const data = await fetchData();
return {
props: { data },
revalidate: 10 // 10秒ごとにページを再生成
};
}revalidateプロパティは、ページをどれだけの頻度で更新するかを決定します。
ISRは、最新情報の提供と高速なページ読み込みのバランスをとるための効果的な方法と言えます。
ページとレンダリング手法
TypeScriptのテクニックとNext.jsの機能
Next.jsでは、TypeScriptの型システムを活用してアプリケーションの堅牢性を高めることができます。TypeScriptは、開発時のエラー検出やコードの自動補完を提供し、大規模なアプリケーション開発において有効です。例えば、Next.jsのページコンポーネントやAPIルートで、入力パラメータや戻り値の型を明確に指定することで、より安全でメンテナンスしやすいコードを書くことが可能になります。
Next.jsは、ウェブサイトやアプリケーションの基本的な構造や機能を提供し、効率的で高性能なプロダクトを作成するフレームワークです。
TypeScriptは、開発時に何が必要で、どのように機能するかを詳細に指定できます。エラーの早期発見や修正、大規模なアプリケーションの保守や拡張が容易になります。
Next.jsを使用する際に、ウェブページの各部分や機能をTypeScriptで記述することで、それぞれの部分が受け取るデータの種類や返すべき内容を正確に定義できます。結果として、コードの間違いが少なくなります。
Next.jsのページとデータ取得
Next.jsを使うと、ウェブページを作る過程で、ページを表示するための情報やデータを取得する方法が提供されます。これは、料理を作る前に必要な材料を集めることに似ています。まず、レシピ(ウェブページの構造)に従って、必要な材料(データ)を集め、料理(ウェブページ)を作ります。
Next.jsでは、「getStaticProps」や「getServerSideProps」といった特別な関数を使って、データを集めます。ウェブページがユーザーに表示される前に、必要なデータがすでに用意されている状態でページが作られます。
例えば、ブログページを作る際には、ブログの記事データを取得し、ページに組み込むことができます。
export async function getStaticProps() {
const data = await fetchData(); // 外部APIからデータを取得
return { props: { data } };
}
const BlogPage = ({ data }) => {
return (
<div>
<h1>ブログページ</h1>
{/* データを表示 */}
</div>
);
};
export default BlogPage;この機能は、SSGやSSRのレンダリング手法と組み合わせることで、ウェブページの読み込み速度を向上させ、検索エンジン最適化(SEO)にも有効です。また、TypeScriptを使用することで、取得するデータの種類が正確になり、より信頼性の高いウェブアプリケーションを構築できます。
SSGによるページの実装
Next.jsの静的サイト生成(SSG)は、事前に大量の食事を準備しておくレストランのシステムに似ています。レストランでは通常、注文を受けてから料理を一から作りますが、事前に多くの料理を作っておけば、客が注文したときにすぐに食事を提供できます。
Next.jsのSSGでは、ウェブサイトを「ビルド」する際、サーバー側でウェブページの全てをあらかじめ生成し、ウェブサイトに配置します。訪問者がそのページを見に来た時、すでに準備されているページを直ちに見ることができます。ページの読み込み時間が短縮され、ユーザーはより早く情報にアクセスできます。
Next.jsでは、getStaticProps関数を使って、ビルド時に必要なデータを取得し、データをページに組み込むことができます。ページが静的に生成されたとしても、最新の情報や動的な内容を含むことが可能です。
// SSGの例
export async function getStaticProps() {
const data = await fetchData(); // データ取得
return { props: { data } };
}
const StaticPage = ({ data }) => (
<div>
<h1>静的ページ</h1>
{/* データをレンダリング */}
</div>
);
export default StaticPage;SSGは、ページの読み込み速度を向上させると同時に、検索エンジン最適化(SEO)にも良い影響を与えます。検索エンジンは、あらかじめ準備されたページをより効率的に認識できるからです。
getStaticPropsを使ったSSGによるページの実装
getStaticPropsを使ったSSGによるページの実装は、「事前に準備された食事の提供」に似ています。あるレストランが、特定のイベントのために事前に多くの食事を準備し、客が到着したらすぐに提供するとします。「getStaticProps」は、イベントのために必要な食材(データ)を集めるプロセスです。レストランのシェフ(サーバー)は、イベントの前に食材を準備し、美味しい料理(ウェブページ)に仕上げます。
Next.jsでは、getStaticProps関数を使って、ウェブページがビルド(準備)される際に必要なデータを取得します。このプロセスはサーバー側で行われ、取得されたデータはページコンポーネントに「props」(プロパティ)として渡されます。ページはあらかじめ必要なデータを含んだ状態で生成され、訪問者に提供されます。
たとえば、ブログページを作る場合、getStaticPropsを使ってブログの記事データを事前に取得し、ページを構築します。訪問者は、ページを開いた瞬間に最新のブログ記事を読むことができます。
ウェブページの読み込み速度を向上させるとともに、訪問者に迅速に情報を提供する効果的な方法です。
// getStaticPropsの例
export async function getStaticProps() {
const data = await fetchData();
return { props: { data } };
}
const BlogPage = ({ data }) => (
<div>
<h1>ブログ記事</h1>
{/* データをレンダリング */}
</div>
);
export default BlogPage;getStaticPathsを使った複数ページのSSG
Next.jsの「getStaticPaths」を使った複数ページの静的サイト生成(SSG)は、レストランで多くの料理を準備し、メニューにリストアップする作業に例えることができます。
レストランには多くの異なる料理があり、それぞれが独自の材料と調理方法を持っています。レストランのスタッフは、料理を事前に準備し、メニューにそれぞれの料理の名前と説明をリストアップします。このメニューによって、客は欲しい料理を簡単に見つけ、注文できます。
Next.jsでの「getStaticPaths」の使用は、メニュー作成のプロセスに似ています。ウェブサイトには多くのページがあり、それぞれが異なる内容を持っています(例えば、ブログの記事や製品の紹介ページなど)。getStaticPathsは、ウェブサイトの各ページの「場所」(URLやパス)をリストアップする役割を担います。ウェブサイトの訪問者は、必要なページを簡単に見つけることができます。
次に、「getStaticProps」を使って、リストアップされた各ページに必要なデータ(例えば、記事の内容や製品情報)を取得し、ページを生成します。これはレストランで料理を事前に準備し、メニューに合わせて提供するようなものです。
たとえば、ブログのウェブサイトでは、getStaticPathsはブログの各記事に対応するURLのリストを生成します。getStaticPropsはそれぞれの記事のデータを取得して、記事のページを構築します。ウェブサイトは、訪問者が訪れたときにすぐに必要なページを提供できます。
下記のコード例では、getStaticPathsを使って必要なパス(記事のURL)を取得し、getStaticPropsでその記事のデータを取得しています。ArticlePageコンポーネントはそのデータを使ってページを表示します。
// getStaticPathsの例
export async function getStaticPaths() {
const paths = await fetchPaths(); // 必要なパスを取得
return { paths, fallback: false };
}
export async function getStaticProps({ params }) {
const data = await fetchData(params.id);
return { props: { data } };
}
const ArticlePage = ({ data }) => (
<div>
<h1>{data.title}</h1>
{/* コンテンツをレンダリング */}
</div>
);
export default ArticlePage;Next.jsを使うことで、ウェブサイトは効率的かつ効果的に構築され、ページの読み込みが高速になります。また、検索エンジンに最適化されたウェブサイトの作成が可能になります。
SSRによるページの実装
SSRによるページの実装は、レストランで料理を注文してからその場で調理されるシステムに似ています。
レストランに行ってメニューから料理を選ぶと、注文を受けてからキッチンで料理が作られます。料理が完成すると、テーブルに運ばれ、すぐに食べることができます。このプロセスは、注文に基づいて個別に料理が準備されるため、客は常に新鮮でカスタマイズされた料理を楽しむことができます。
Next.jsのSSRでは、このプロセスがウェブページで行われます。誰かがウェブサイトにアクセスすると、リクエストに応じてサーバー上でページが「調理」されます。サーバーはリクエストのためにページを実際に生成し(レンダリング)、完全に構築されたページ(HTML)をユーザーのブラウザに送信します。ページの初期表示が可能になり、特に検索エンジン最適化(SEO)やパフォーマンスに重点を置いたアプリケーションに効果的です。
getServerSideProps関数は、各リクエストに応じて必要なデータを取得する役割を果たします。サーバー上で完全に構築されたページがクライアントに送信され、訪問者はすぐにページの内容を見ることができます。
// SSRの例
export async function getServerSideProps(context) {
const data = await fetchData(); // リクエスト毎にデータを取得
return { props: { data } };
}
const ServerRenderedPage = ({ data }) => (
<div>
<h1>サーバーレンダリングページ</h1>
{/* データをレンダリング */}
</div>
);
export default ServerRenderedPage;ISRによるページの実装
ISRは、自動更新機能を持つ案内板のようなものです。
あるレストランがメニューを表示するために案内板を使っているとします。この案内板は特別で、一定の間隔で自動的に最新の情報に更新されます。たとえば、毎朝レストランのスタッフがその日の特別メニューを設定しますが、その後は案内板が10分ごとに自動的に新しいメニュー情報を表示するように更新されます。レストランの来客は、いつも最新のメニュー情報を確認できます。
Next.jsのISRは、自動更新案内板のように機能します。ウェブページは最初に「ビルド」されるときに静的に生成されます(レストランで朝に設定されたメニュー)。その後、定義した時間間隔(例えば10秒ごと)でページは自動的に再生成され、最新の情報に更新されます。
このプロセスは、getStaticProps関数にrevalidateキーを設定することで行われます。
// ISRの例
export async function getStaticProps() {
const data = await fetchData();
return {
props: { data },
revalidate: 10 // 10秒ごとにページを再生成
};
}
const IncrementalStaticRegeneratedPage = ({ data }) => (
<div>
<h1>インクリメンタル静的再生成ページ</h1>
{/* データをレンダリング */}
</div>
);
export default IncrementalStaticRegeneratedPage;ISRにより、ウェブページは静的サイトの高速なロード時間の利点を維持しつつ、定期的に内容が更新されることで常に最新の状態を保つことができます。
Next.jsの機能
Next.jsは、ウェブサイトやウェブアプリケーションを作るためのツールの一つです。Next.jsは、Reactをベースにしています。Next.jsはウェブ開発をより簡単かつ効率的にするための多くの便利な機能を提供します。
- サーバーサイドレンダリング: ウェブページがユーザーに表示される前に、サーバー側でページの内容を準備する方法です。ページの読み込みが速くなり、検索エンジンでの表示(SEO)も向上します。
- 静的サイト生成: ウェブサイトのページを事前に作成しておくことができ、ユーザーがアクセスした時に高速で表示されます。
- APIルート: ウェブアプリケーションが外部のデータや機能とやり取りするための方法を簡単に設定できる機能です。
- 画像最適化: ウェブサイトに掲載される画像のサイズや品質を自動的に最適化し、ページの読み込み速度を高めます。
- 国際化: 異なる国や言語のユーザー向けにウェブサイトを簡単に調整できる機能です。
- 環境変数の管理: ウェブアプリケーションの設定を安全かつ効率的に管理できます。
Next.jsの最大の利点は、各機能を簡単に利用できることです。速くて、SEO(検索エンジン最適化)に強いウェブアプリケーションを構築できます。
リンク
Next.jsでの「リンク」は、ウェブページ間を移動するための方法です。リンクは特に「Linkコンポーネント」と呼ばれる機能を使って行われます。リンクを使うと、ウェブページを再読み込みすることなく、スムーズに別のページに移動できます。リンクにより、ユーザーはより快適にウェブサイトを利用できます。
あるページから別のページにリンクをクリックするだけで、すぐに新しいページが表示されます。通常のウェブページでは、リンクをクリックすると新しいページが完全に読み込まれるまで待つ必要がありますが、Next.jsではこのプロセスが高速化されています。
以下は、Next.jsでのリンクの設定例です。例えば、ウェブサイトに「アバウトページ」と「コンタクトページ」へのリンクを設定したい場合、以下のようなコードを使って設定します。
import Link from 'next/link';
const Navigation = () => (
<nav>
<Link href="/about"><a>アバウトページ</a></Link>
<Link href="/contact"><a>コンタクトページ</a></Link>
</nav>
);上記のコードは、ウェブサイトのナビゲーション部分に「アバウトページ」と「コンタクトページ」へのリンクを作成しています。ユーザーがリンクをクリックすると、関連するページに迅速に移動します。
画像の表示
Next.jsでは、「Imageコンポーネント」という特別な機能を使って、ウェブサイト上で画像を表示し、画像を最適化します。Imageコンポーネントにより、画像のロード時間が短縮され、ウェブサイトのパフォーマンスが向上します。訪問者にとって、快適な体験が提供されます。
Imageコンポーネントが行う最適化には、以下の機能が含まれます。
- 画像サイズの自動調整: 画像が表示される場所に応じて、適切なサイズに自動的に調整されます。
- 遅延読み込み: ユーザーが画像が表示される部分までスクロールするまで、画像の読み込みを遅らせることで、初期のページ読み込み速度を向上させます。
- 画像形式の変換: ウェブブラウザに最適な形式で画像を提供します。
以下は、Next.jsで画像を表示するコードの例です。
import Image from 'next/image';
const MyImage = () => (
<div>
<Image
src="/path/to/image.jpg" // 画像のパス
alt="説明テキスト" // 画像の説明テキスト
width={500} // 画像の幅
height={300} // 画像の高さ
/>
</div>
);上記のコードでは、指定したパスにある画像をウェブサイトに表示し、サイズを幅500ピクセル、高さ300ピクセルに設定しています。また、「説明テキスト」は画像が何を表しているかを説明するためのものです。
Next.jsのImageコンポーネント機能により、ウェブ開発の生産性と効率性が大きく向上します。
APIルート
Next.jsの「APIルート」とは、ウェブサイトの背後で動作する特定の機能やデータを管理するツールです。Next.jsのAPIルートを「レストランの注文システム」に例えてみましょう。
あなたがレストランにいて、メニューから何かを注文します。この時、ウェイターがあなたの注文を聞いて、厨房に伝える役割を果たします。厨房ではその注文に基づいて料理が準備され、完成したらあなたのテーブルに運ばれます。
Next.jsのAPIルートも同様に機能します。ウェブサイトでユーザーが何かアクション(例えばボタンをクリックしたり、何か情報を入力したり)をすると、その情報は「APIルート」(この場合のウェイター)を通じてサーバー(厨房)に送られます。サーバーはこの情報をもとに何らかの処理(料理の準備)を行い、その結果をユーザーに返します(料理がテーブルに運ばれる)。
「APIルート」の利点は、サーバーで行われる処理を柔軟に設定できることです。厨房でさまざまな種類の料理を作れるように、ウェブサイトの裏側でデータベースへのアクセス、ユーザー認証、他のサービスとのデータ交換など、様々な作業を行えることを意味します。
APIルートはウェブサイトとサーバー間の通信を取り仕切るウェイターのような役割を果たし、ユーザーの要求に応じてサーバーで必要な作業を行い、結果をユーザーに返す仕組みです。
Next.jsでは、APIルートを設定するために「pages/api」ディレクトリ内にファイルを作成します。それぞれのファイルは、ウェブサイトの特定のURLにアクセスしたときに実行される「APIエンドポイント」を表します。
以下は、Next.jsで簡単なAPIエンドポイントを作成する例です。
// pages/api/hello.js
export default function handler(req, res) {
res.status(200).json({ message: 'Hello!' });
}上記のコードは「/api/hello」というURLにアクセスすると、画面に「Hello!」というメッセージが表示されるように設定しています。ウェブサイトのバックエンドで、簡単なデータのやり取りを行うことができます。
環境変数/コンフィグ
Next.jsでは、「環境変数」と呼ばれる機能を使って、ウェブサイトやアプリケーションの重要な設定情報(例えば、データベースへの接続情報やAPIキーなど)を安全に管理できます。環境変数は、ウェブサイトが動作するサーバー上で設定され、プログラムが動く際に使われます。
APIキーなどの情報は通常、他人に見られたくない機密性の高いものです。そこでNext.jsでは、機密性の高い情報を「.env.local」という特別なファイルに保存することが推奨されています。「.env.local」ファイルはプロジェクトのルート(基本的なディレクトリ)に置かれ、セキュリティを確保しながら必要な設定情報を提供します。
例えば、以下のように情報を設定できます。
API_KEY=your_api_key_here // あなたのAPIキー
DATABASE_URL=your_database_url_here // データベースへの接続URL「.env.local」で設定された変数は、サーバーサイドのコード内で「process.env」という方法でアクセスできます。プログラムがサーバー上で動作する際に、機密情報を安全に使用できます。
Next.jsの環境変数を活用することで、アプリケーション開発はより効率的かつ安全に行うことができます。
コンポーネント開発
ReactとNext.jsを使ったコンポーネント開発は、現代のウェブ開発の中心的な部分です。「コンポーネント」とは、ウェブサイトやアプリケーションを構成する個々の部品のことです。コンポーネントを組み合わせることで、ウェブサイト全体が形成されます。
TypeScriptの開発で重要な型とReact/Next.jsのコンポーネント開発
コンポーネント開発の過程で、TypeScriptが重要な役割を果たします。TypeScriptは「型安全性」という概念を提供し、開発者はプログラム内の各種データが正しい形(型)であることを確保できます。特に大規模なアプリケーションの開発において、エラーやバグを予防するのに役立ちます。
ReactとNext.jsでは、TypeScriptはコンポーネントの「Props」(コンポーネントに渡されるデータ)、「State」(コンポーネントの状態を管理するデータ)、イベントハンドラ(ユーザーの操作に反応して実行される関数)などの型定義に使われます。開発者はコンポーネント間でのデータのやり取りをより明確に理解し、安全にコードを記述できます。
例えば、以下のコードはTypeScriptを使用した簡単なReactコンポーネントを示しています。
type GreetingProps = {
name: string;
};
const Greeting: React.FC<GreetingProps> = ({ name }) => {
return <div>Hello, {name}!</div>;
};上記のコードでは、GreetingPropsという型を定義し、nameプロパティを文字列として指定しています。もしnameプロパティが提供されない場合や非文字列が渡された場合に、TypeScriptが警告を出してくれます。
TypeScriptを使用することで、ReactとNext.jsでのコンポーネント開発がより効率的で信頼性の高いものになります。開発者は、より堅牢なアプリケーションを構築できます。
Atomic Designによるコンポーネント設計
Atomic Designは、ウェブインターフェースやアプリケーションのコンポーネント(ウェブページの構成要素)を設計する方法です。Atomic Designは、化学の「原子」から着想を得ており、ウェブページを構成する要素を小さいものから大きなものへと段階的に組み立てることが推奨されています。
Atomic Designにより、ウェブページのデザインや機能をより効率的に再利用し、管理しやすくなります。
- 原子 (Atoms): UI(ユーザーインターフェース)の最小単位です。例えば、ボタン、入力フィールド、ラベルなどがこれに当たります。単独ではシンプルですが、組み合わせることでより複雑な機能を形成します。
- 分子 (Molecules): 分子は複数の原子を組み合わせたものです。例えば、テキストボックスと検索ボタンが組み合わさって検索フォームを形成します。具体的な機能を果たします。
- 有機体 (Organisms): 有機体は複数の分子(または原子)を組み合わせたものです。例えば、ウェブページのヘッダーやフッターがこれに当たり、ウェブページの特定のセクションを形成します。
- テンプレート (Templates): テンプレートはページの基本的なレイアウトを定義します。有機体、分子、原子をどこに配置するかを決めます。
- ページ (Pages): ページはテンプレートに具体的なコンテンツを充填したもので、ウェブサイトの最終的な見た目を表します。
- Presentational Component: UIの見た目に焦点を当てたコンポーネントです。主に見た目やスタイルに関わる部分です。
- Container Component: データの取得や状態管理など、より複雑なビジネスロジックに関わるコンポーネントです。
Atomic Designにより、UIのデザインとビジネスロジックを別々に管理しやすくなり、コンポーネントを再利用しやすく、テストしやすくなります。
Atomic Designはウェブ開発において、より整理され、効率的かつ一貫性のあるアプローチを提供します。特に、ReactやNext.jsのようなモダンなウェブ開発フレームワークとの相性が良いです。
styled-componentsによるスタイリング実装
「styled-components」とは、React.jsやNext.jsを使用したウェブ開発において、ウェブページのスタイル(見た目やデザイン)を設定するための便利なツールです。styled-componentsは「CSS-in-JS」というアプローチを採用しています。CSS-in-JSは、JavaScriptのコード内で直接CSS(ウェブページのスタイルを定義する言語)を書く方法です。CSS-in-JSを使うと、ウェブページを構成する各コンポーネントのスタイルを個別に管理しやすくなります。
styled-componentsの利点は、スタイルの「スコープ」の問題を解決することです。通常のCSSでは、あるスタイルが予期せず他の部分にも影響を与えることがあります。しかし、styled-componentsを使用すると、それぞれのスタイルは特定のコンポーネントにのみ適用されるため、スコープ問題を避けることができます。また、コンポーネントの再利用性やメンテナンス性も向上します。
styled-components を Next.js に導入
Next.jsプロジェクトにstyled-componentsを導入するステップは、以下の通りです。
- 必要なパッケージ(styled-componentsとBabelプラグイン)をインストールします。BabelはJavaScriptのコードを変換するツールで、styled-componentsを適切に動作させるために使用します。
- プロジェクトのルートにカスタムの.babelrcファイルを作成し、styled-componentsのプラグイン設定を追加します。サーバーサイドレンダリング(ウェブページがユーザーに表示される前にサーバー側でページの内容を準備するプロセス)時にもスタイルが適切に適用されます。
具体的には、以下のようにコマンドを実行してパッケージをインストールし、.babelrcファイルに設定を追加します。
npm install --save styled-components
npm install --save-dev babel-plugin-styled-components{
"presets": ["next/babel"],
"plugins": [["styled-components", { "ssr": true }]]
}Next.jsのプロジェクトでstyled-componentsを効果的に使用し、ウェブページのスタイリングを容易に管理できます。
styled-componentsを用いたコンポーネント実装
「styled-components」を使うと、React.jsやNext.jsでウェブページのデザインを行う際に、スタイル(見た目や装飾)を簡単にコンポーネント(ウェブページの個々の部品)に適用できます。styled-componentsでは、スタイルの定義とコンポーネントのロジック(動作や機能)が一箇所にまとまるため、コードの整理や管理がしやすくなります。
具体的には、以下のような手順でコンポーネントにスタイルを適用します。
- まず、
styled-componentsをインポートします。 - 次に、特定のHTML要素(この例では
button)にスタイルを適用するための新しいコンポーネントを作成します。このコンポーネントは、テンプレートリテラル(バッククォート ` を使用した文字列)を使って直接CSSを記述します。
例えば、以下のコードは青い背景と白い文字を持つボタンを作成し、マウスホバー時に背景色を濃紺に変更するスタイルを定義しています。
import styled from 'styled-components';
const Button = styled.button`
background-color: blue;
color: white;
padding: 10px 20px;
border: none;
border-radius: 5px;
cursor: pointer;
&:hover {
background-color: navy;
}
`;Buttonコンポーネントをページに追加すると、指定されたスタイルが適用されたボタンが表示されます。
styled-componentsの使用により、React.jsとNext.jsのプロジェクトではスタイリングの柔軟性と一貫性が高まります。デザインシステムやテーマの管理にも適しており、大規模なアプリケーション開発においても効果的です。開発者は見た目と機能を簡単に組み合わせ、美しく機能的なウェブページを作成できます。
Storybookを使ったコンポーネント管理
Storybookは、React.jsやNext.jsを使用するウェブ開発において、コンポーネント(ウェブページの個々の部品)を管理するのに便利なツールです。Storybookは、開発中のコンポーネントを個別に開発し、テストするのを助けます。Storybookを使用すると、UI(ユーザーインターフェース)コンポーネントのカタログを作成し、各コンポーネントを独立した環境で視覚的に確認できます。
Storybookの基本的な使い方
Storybookの基本的な使い方は以下の通りです。
- Storybookのインストール: StorybookのCLI(コマンドラインインターフェース)ツールを使用して、プロジェクトに必要な依存関係をインストールします。コマンドラインでの簡単なコマンド実行で行えます。
- 設定ファイルの作成: 次に、
.storybookというディレクトリをプロジェクト内に作成し、設定ファイルを配置します。 - ストーリーの作成: コンポーネント毎に「ストーリー」と呼ばれるファイルを作成します。ストーリーでは、コンポーネントの使い方や状態を定義します。
例えば、以下のコードはボタンコンポーネントのストーリーを示しています。
// 例:Button.stories.js
import React from 'react';
import { Button } from './Button';
export default {
title: 'Button',
component: Button,
};
export const Primary = () => <Button primary>ボタン</Button>;上記のコードでは、ボタンコンポーネントについてのストーリーが定義されており、開発者はこのストーリーを通じてボタンの見た目や動作を確認できます。
Storybookを使用することで、開発者はコンポーネントをより効率的に管理し、開発過程をスムーズに進めることができます。また、チームメンバー間でのコンポーネントの共有やコミュニケーションも容易になります。
Actionを使用したコールバックのハンドリング
Storybookの「action」機能は、ウェブサイトやアプリケーションのコンポーネント(例えばボタン)がどのように動作するかをテストするのに役立ちます。特に、ユーザーの操作(例えばクリック)に対するコンポーネントの反応を確認する際に使用されます。actionは、コンポーネントに何かしらの操作が行われた時の振る舞いを視覚的に確認するものです。
具体的には、action機能を使うことで、例えば「ボタンがクリックされた時に何が起こるか」というような情報をStorybookのユーザーインターフェース上にログとして表示できます。開発者は、コンポーネントが正しく動作しているかを簡単に確認できます。
以下のコードは、クリックイベントが発生した時に何が起こるかをテストするためのボタンコンポーネントのストーリーです。
import React from 'react';
import { Button } from './Button';
import { action } from '@storybook/addon-actions';
export default {
title: 'Button',
component: Button,
};
export const WithAction = () => (
<Button onClick={action('button-click')}>クリック</Button>
);上記のコードでは、ボタンをクリックすると「button-click」というアクションがトリガーされ、StorybookのUI上でログとして表示されます。開発者やデザイナーは、コンポーネントが予期した通りに反応しているかを簡単に確認できます。
Storybookを使用することで、コンポーネントの開発をより効率的に進めることができ、デザイナーや他の開発者とのコミュニケーションも容易になります。また、コンポーネントの再利用性を高め、一貫性のあるUIを構築するのにも役立ちます。
Controlsタブを使ったpropsの制御
Storybookの「Controls」タブは、ウェブ開発の際に使用するコンポーネント(例えばボタン)の特性(propsと呼ばれる)をリアルタイムで調整し、結果をすぐに確認できる便利なツールです。Controlsを使うと、開発者はコンポーネントのさまざまな設定(例えば色やサイズ)を簡単に変更し、見た目や動作にどのように影響するかをすぐに確認できます。
例えば、ボタンの色やサイズを動的に変更して、ボタンが異なる状態でどのように見えるかを確認できます。コンポーネントの柔軟性や再利用性を高めます。
以下は、ボタンコンポーネントのためのStorybookストーリーの例です。ボタンの色やサイズを制御する設定が含まれています。
// Button.stories.js
import React from 'react';
import { Button } from './Button';
export default {
title: 'Button',
component: Button,
argTypes: {
color: { control: 'color' },
size: { control: { type: 'select', options: ['small', 'medium', 'large'] } },
},
};
export const Primary = (args) => <Button {...args}>ボタン</Button>;上記のコードでは、「color」は色を選択するためのコントロールを、「size」はサイズを選択するためのドロップダウンメニュー(小、中、大)を提供します。開発者は各オプションを変更することで、ボタンがどのように見え、動作するかをリアルタイムで確認できます。
StorybookのControlsタブを使用することで、コンポーネントの開発とテストがより簡単で効率的になります。
アドオン
Storybookの「アドオン」とは、Storybookの基本機能を拡張し、ウェブ開発プロセスを強化する追加ツールです。アドオンを使用することで、開発者やデザイナーはコンポーネントのデザインや機能に関してより深い理解を得ることができます。また、チームメンバー間での協力も効果的になります。
Storybookにはさまざまなアドオンが用意されており、以下のような機能を追加できます。
- アクセシビリティのチェック: ウェブサイトがさまざまなユーザーにとって使いやすいかどうかを評価します。
- 背景色の変更: デザインが異なる背景色でどのように見えるかをテストできます。
- レスポンシブデザインの確認: ウェブサイトが異なる画面サイズやデバイスでどのように表示されるかを確認できます。
- ソースコードの表示: コンポーネントのソースコードを表示し、コードの理解を深めます。
アドオンをインストールするには、通常、特定のコマンドを実行して必要なパッケージをプロジェクトに追加します。例えば、以下のコマンドはアクセシビリティと背景色変更のためのアドオンをインストールします。
npm install @storybook/addon-a11y @storybook/addon-backgrounds --save-devそして、Storybookの設定ファイル(例えば.storybook/main.js)にアドオンを追加します。
module.exports = {
addons: [
'@storybook/addon-links',
'@storybook/addon-essentials',
'@storybook/addon-a11y',
'@storybook/addon-backgrounds'
],
};Storybookのアドオンを使用することで、ReactやNext.jsを使用したコンポーネント開発がより効率的かつ協力的になり、デザイナーや開発者が共同してUIを制作できます。
コンポーネントのユニットテスト
ユニットテストとは、ウェブ開発において、アプリケーションを構成する個々のコンポーネントが正しく動作することを確認するテストのことです。React、TypeScript、Next.jsを使ったプロジェクトでは、ユニットテストが特に重要です。ユニットテストを行うことで、各コンポーネントが予定通りに機能しているかを確認し、将来的なエラーやバグを早期に発見できます。
Reactにおけるユニットテスト
Reactでのユニットテストでは、通常、以下のようなことをチェックします。
- コンポーネントが正しく表示されるか(レンダリング)
- ユーザーの操作(クリックなど)に対してコンポーネントが正しく反応するか
各テストを行うために、React Testing LibraryやJestといったツールが一般的に使用されます。コンポーネントのテストを容易にし、コードが期待通りに動作するかを自動的にチェックします。
以下のコードは、ボタンコンポーネントのテスト例です。
// Button.test.js
import React from 'react';
import { render, screen } from '@testing-library/react';
import Button from './Button';
test('renders a button with text', () => {
render(<Button>クリック</Button>);
expect(screen.getByText('クリック')).toBeInTheDocument();
});上記のテストでは、「クリック」というテキストを持つボタンが正しく画面に表示されるかを確認しています。テストを実施することで、アプリケーションの各部分が正しく機能していることを確認し、より信頼性の高いウェブサイトやアプリケーションを開発できます。
テスト環境構築
Reactを使ったウェブアプリケーションのコンポーネントが正しく動作するか、テスト環境を構築できます。テスト環境の構築は、アプリケーションの品質を確保し、後にコードを変更したり機能を追加したりする際に、既存の機能が正しく動作し続けることを確認するために重要です。
テスト環境を構築するステップは、以下の通りです。
- 必要なテストライブラリのインストール: まず、テストに必要なライブラリをインストールします。
Jestは、Reactアプリケーションのテストを実行するためのツール(テストランナー)です。React Testing Libraryは、ウェブページのDOM(ドキュメントオブジェクトモデル、つまりページの構造)要素を操作し、テストするための便利な機能を提供します。
コマンドでこれらをインストールするには、以下のように実行します。
npm install --save-dev jest @testing-library/react @testing-library/jest-dom- テストの設定ファイルの作成: 次に、
jest.config.jsという設定ファイルを作成し、テスト環境をカスタマイズします。テストを実行する際の特定の設定を定義できます。
設定ファイルの一例は以下の通りです。
// jest.config.js
module.exports = {
setupFilesAfterEnv: ['@testing-library/jest-dom/extend-expect'],
testPathIgnorePatterns: ['/node_modules/', '/.next/'],
// その他の設定...
};各設定を行うことで、React、TypeScript、Next.jsを使用したプロジェクトの開発において、各コンポーネントが期待通りに動作するかを確認するためのテスト環境が整います。テスト環境は、アプリケーションの品質を保証し、安心してコードのリファクタリング(改善)や新機能の追加を行うための基盤となります。
React Testing Libraryによるコンポーネントのユニットテスト
React Testing Libraryは、Reactで作られたコンポーネントをテストする専用ツールです。React Testing Libraryの主な目的は、ユーザーが実際に使う時の視点でコンポーネントの機能をテストすることです。ウェブページのボタンがクリックされたときや入力フィールドに文字が入力されたときなど、実際の操作に対するコンポーネントの反応をチェックします。
React Testing Libraryを使用することで、DOM(ウェブページの構造)要素の表示(レンダリング)、ユーザー操作(イベントハンドリング)に対する反応、フック(Reactの機能を拡張するためのコード片)の動作などを効率的にテストできます。
以下は、ボタンコンポーネントのクリックイベントをテストするコードです。
import { render, fireEvent } from '@testing-library/react';
import Button from '../Button';
test('Button click event', () => {
const handleClick = jest.fn(); // クリックイベントをシミュレートするための関数
const { getByText } = render(<Button onClick={handleClick}>クリック</Button>); // ボタンをレンダリング
fireEvent.click(getByText('クリック')); // ボタンをクリックするイベントを発生させる
expect(handleClick).toHaveBeenCalledTimes(1); // ボタンが一回クリックされたことを確認
});上記のテストでは、ボタンがクリックされたときに適切な関数が呼び出されるかどうかを確認しています。React Testing Libraryを使用すると、コンポーネントがユーザーの操作に対して適切に反応するかを確認しやすくなり、より信頼性の高いウェブアプリケーションを作成できます。
非同期コンポーネントのユニットテスト
非同期コンポーネントのユニットテストとは、ウェブアプリケーションの一部であるコンポーネント(例えば、データをインターネットから取得して表示する部分)が、データを取得するなどの「待ち時間が必要な処理」を含む場合のテストのことです。通常のテストと異なり、データの取得などの処理が完了するのを待つ必要があります。
React Testing Libraryは、非同期処理を含むコンポーネントのテストに役立つ機能(waitForやfindByなど)を提供しています。各機能を使うことで、データの取得やその他の処理が完了するまで待ち、その後でテストを続けることができます。
例えば、以下のコードでは外部のAPIからデータを取得して表示するコンポーネントをテストしています。
import { render, waitFor } from '@testing-library/react';
import FetchComponent from '../FetchComponent';
test('loads and displays data', async () => {
const { getByTestId } = render(<FetchComponent />);
await waitFor(() => getByTestId('fetched-data')); // データが取得されるまで待つ
expect(getByTestId('fetched-data')).toHaveTextContent('取得したデータ'); // 取得したデータが表示されているかを確認
});上記のテストでは、waitFor関数を使用してデータがフェッチ(取得)され、画面に表示されるのを待っています。その後、取得したデータが期待通りに表示されているかを確認しています。
非同期処理を含むコンポーネントのテストにより、ウェブアプリケーションの各部分が正しく動作するかをより確実に確認できます。
まとめ
TypeScript、React.js、Next.jsの基礎について解説しました。
TypeScriptはJavaScriptの「上位互換」のようなもので、より安全なコードを書けるようにするものです。Visual Studio Codeなどのエディターを使って、TypeScriptのコードを書いたり、チェックしたりできます。
React.jsは、ウェブページの一部分を作るためのツールです。コンポーネントという小さな部品を作って、組み合わせてページを作ります。React.jsでは、データの流れを管理する「フック」という機能も使います。
Next.jsはReact.jsを使ったウェブアプリを作るためのフレームワークです。ページをどのように表示するか(例えば、事前に生成するか、リアルタイムで生成するか)を決める方法などがあります。
コンポーネントをデザインするためのAtomic Design、スタイリングにはstyled-components、コンポーネントの管理にはStorybookというツールも紹介しました。React Testing Libraryを使って、作ったコンポーネントが正しく動くかどうかをテストする方法も解説しました。
TypeScript、React.js、Next.jsの基礎を学ぶことで、アプリ開発のスキルが身につきます。まずは基本から始めて、徐々に知識を広げ、アプリを開発してみましょう。

▼AIを使った副業・起業アイデアを紹介♪